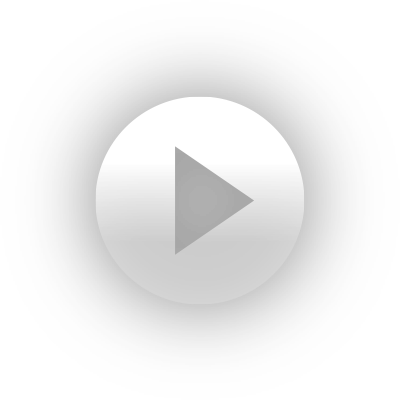標高2999m、360度の大パノラマが広がる剱岳の頂上
【360度パノラマビュー】

剱岳山頂

剱嶽社の祠

標高2997.07mの三等三角点

剱沢カール

1907年に柴崎芳太郎が登ったルート

その左に五龍岳が見える東方向の景色

その右に鑓ヶ岳が見える北方向の景色

コメント
2004年に、標高が2998mから2999mに変更された剱岳山頂。
岩に覆われた一番高いところに剱嶽社の祠があり、そこに立つと360度の景色が眺められ、これこそ、山の頂上と言えるような場所でした。
登頂して、まず最初に目指したのが三等三角点。映画「劒岳 点の記」を見て、本も読み、この三角点がココに設置されたことは本当に素晴らしいと思います。
今から100年前、登頂不可能と言われていた剱岳に三角点を設置するため、測量隊が何度もアタックしました。しかし、失敗の連続で、そんな中、1907年、測量士・柴崎芳太郎を始めとする測量隊が登頂に成功。このときに計測した標高が2998mだったことは、当時の測量技術がいかに高かったか分かります。
しかし、登るのも困難な山のため、機材を運び上げることができず、結局、標石のない四等三角点となりました。そのため、長い間、剱岳には三角点標石がありませんでしたが、測量登頂100周年を記念して、2004年8月に三等三角点が設置されました。